【タイトル】カラハリが呼んでいる
【著者】マーク・オーエンズ&ディーリア・オーエンズ
【出版社】早川書房(2021.08.15.発売)
ある動画にて角幡雄介さんが紹介していた書籍。すぐに購入するべくAmazonで探したところ、総ページ数が700ページ超え…直前で「謎の独立国家 ソマリランド(高野秀行さん著)」の高ボリュームを読んだ後だけに少し怯んだが、家族の後押しもあり?思い切って購入した。
到着した書籍は薄い単行本であれば3冊分の厚さほど…少しどころではなく、結構怯んだが、いざ読み始めると主人公であるマークとディーリア(アメリカ人夫妻)の好奇心と研究者魂、そして未知の世界へ潔く踏み込んで行くふたりのカリハラ砂漠での生活に一気にのめり込んで行くのであった。
ライオンやカッショクハイエナ、ジャッカルなどの関連性やそれぞれの社会性など、雨季と乾季で生活手段が大きく変化する砂漠での生き方を、またカラハリ砂漠が抱えている現状の問題に向ける熱い活動(思い)を明快な解説で追い続ける傑作ドキュメンタリー作品であると思う。
人間は食べられない?
マークとディーリアが調査のベースとなるディセプション・ヴァレーにキャンプを設営した時、ライオンやカッショクハイエナたち砂漠に住む野生動物たちは人間に遭遇したことがないという状態であった。動物たちからしたら、見たことがない直立する、ヒョロヒョロな生き物(雄雌の区別は感じたのであろうか…)がやってきた事に当惑したに違いない。
二人が動物たちを観察するのと同じ様に、動物たちも二人を遠目でくまなく注視していたのだろう。そして自分たちに害を及ぼす存在でない事を感じ、次第にちょっかいを出したりして意思の疎通?的なふれあいを行う様にまでなっていく。
ライオンは空腹になると狩猟を行い、スプリングボックなどの被捕食動物を捕まえる。そのおこぼれをカッショクハイエナやジャッカルなど屍肉食者が狙っている。弱肉強食は言わずもがな、野生の厳しい世界がそこにある。そこにフラッと人間が現れて、動物たちのテリトリーを(調査の為)ウロウロしているのだが、彼らが捕食されることはなかった。
なぜ捕食動物たちは二人を襲わなかったのか、幼獣については親の刷り込み的な現象が起こっていたのだろうかとても不思議であり興味深く感じた。そしてライオンとカッショクハイエナの生態についても、動物たちとの距離を縮めるときと同様に、毎晩根気よく動物たちの徘徊を追い続け、雨季と乾季、及び旱魃を耐えて実に7年の年月、その生態を解き明かしていった事に尊敬の念を抱いた。
また動物たちの調査研究だけでなく、現地に住む人々との交流なども一筋縄ではない面白さがあり、物語に緩急を与えている。
変化を望む人達ばかりではない?
巻末の解説にて、高田明さんが指摘しているように、実際にカラハリで生活している現地人たちの気持ちにどれだけ寄り添っていたのか、その部分については私も若干気になりながら(少し冷静に距離をとり)読み続ける部分があった。
近代社会に生きる我々(欧米~先進国の人々)は、効率と快適、そして豊かな生活を長年求め、地球の資源を乱用、環境を破壊してきたのではないか、という思いが少なからずある。山は切り拓かれ、土地はコンクリートに覆われ、密閉度を高めた住居は外界を遮断しており、生活はとても快適だ。快適な生活を送るためには、そのインフラを維持するために経済(自然から分断された社会の)を回す必要があり、我々はその経済の中で生きてゆく事になるが、自然界に比べればその世界はとても快適で楽しい事も多いと思う。
そして発展途上国の人々だって様々な支援を受けながらも、その土地で豊かな生活が送れる様、欧米の生活様式なども取り入れながら、生活水準を向上させてゆく事を望むであろう。快適で楽な生活を送りたいのは同じ人間としてみな一緒であろう。
我々はこのままでは地球が滅亡するであろうことを知っている -だから今この様な政策(施策)を行っている事はナンセンスだ、即刻辞めるべきだー と、今まで我々は大切な地球を粗末に扱ってきたにも関わらず、そんな事は棚の上において、能書きを垂れるのである。途上国の人々や、これからの世代(子孫)には我慢を強要するだけなのである。(自分もそのうちの一人である事は間違いないが、、)やはり心の中で「勝手だな…」と思う。(もちろんただ我慢を強いるのではなく、今までの経験、蓄積された実績を用いた代替案があっての事だとは思うが。)
総括
少なくとも彼らは(マークとディーリア)、動物たちの為に私財をなげうってまで日々奔走する姿が印象的であり、その熱意には心を揺さぶられるそんな気持ちになった。一寸先は闇…な荒野で生きる彼らの生活は、山奥でこの先へ踏み込んだら後戻りは難しくなるだろう(もちろん先の状況だって不明である)、という状況と何ら変わることない、即ち大冒険と言ってもなんら過言ではないと感じた。
50年前、私が産まれた頃の話に心が熱くなった。この本を読むことが出来て本当に良かったと思う。

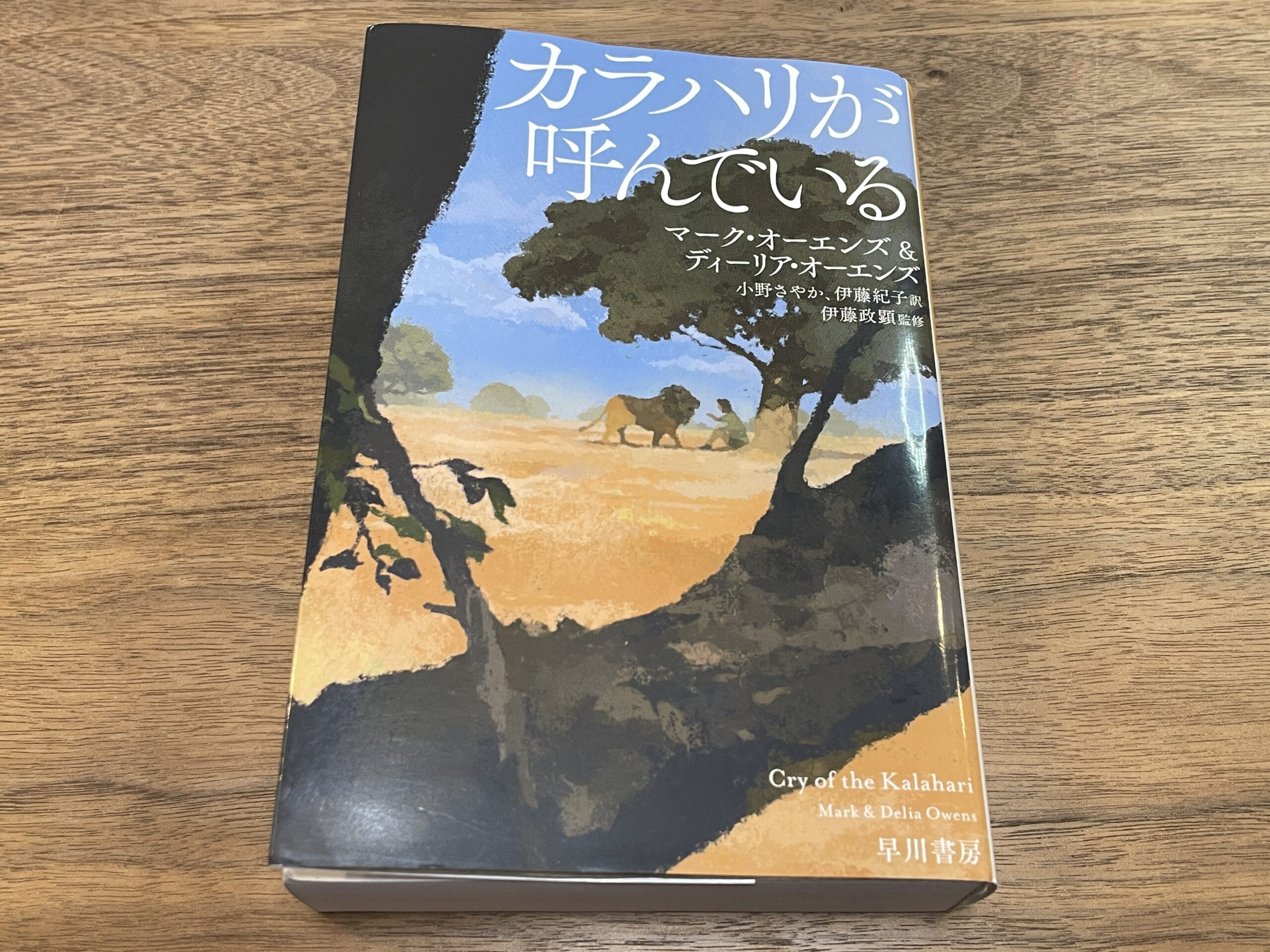


コメント