【タイトル】幻獣 ムベンベを追え
【著者】高野 秀行
【出版社】集英社文庫(2003.01.25.発売)
高野秀行さんと言えば、アフリカを舞台として、現地に潜り込み、生活する人々の文化を判り易く、面白く、そして真摯に伝えてきたノンフィクション作家である。これまで「謎の独立国家 ソマリランド」、「酒を主食とする人々」と著者の作品を読み、その地域に密着した取材・ドタバタ劇にまいど引き付けられ、ついに原点となる本書「幻獣 ムベンベを追え」を手にすることとなった。
本書を読み進めて、先ず関心してしまったのは、20歳そこそこの若者(高野さん)の行動力、それも計画から実行へと、とてもロジカルに進められていることである。ふと私が20歳であった時の状況を思い出し、その余りにも乖離する活動っぷり、その違いの度合いに、比較するものではないとは思いつつも、その燦燦とした生き様に憧憬の念を抱いてしまった。
若者だからこその行動力=思い切りの良さは、良くも悪くも、時に無計画で成り行き任せなものとなることが多いであろう。しかし高野さんは出発前にすべき計画から準備まで、それは人員の確保、コンゴ政府へのコンタクト、現地での言葉であるフランス語の習得や、探査に必要な道具の調達(科学的に探査するための望遠カメラ、ビデオ、高性能マイク、夜間暗視装置などの機器から食料や生活雑貨の諸々)、出発前の合宿などなど、その方面の関係者達と積極的に接触し、たくさんの交渉をこなすのであった。
この一人で生き抜くための力とでも言おうか、「何をするべきか」と考えるのではなく、身体が勝手に最適解となるものを求めて動き出している様な、とてもマルチな才能を発揮する高野さんの人間性こそ、今もノンフィクション作家として第一線で活躍する所以なのだろうと感じた。
高野さんを中心に結成されたコンゴ・ドラゴン・プロジェクト(CDP)のメンバーはタイトルの通り、幻の生き物ムベンベを見つけに。そして仲介役で旅を引っ搔き回す役柄のコンゴ政府のドクター(アニャーニャー博士)はコンゴという国を世界に発信・アピールする一つの手段として、ムベンベの存在を都合よく利用したかったのであろうか。またムベンベが潜むテレ湖の玄関口となるボア村の人々は、金稼ぎのためにムベンベ探査に協力はするものの、大事にするのはアフリカの土地に生きる先住民としての生き方、自然との共存であり、ムベンベの言い伝え(伝説)もその中の一つに過ぎず、見つかろうが見つからなかろうがどうでも良かったのだろう。
そんな一癖二癖ある面々がムベンベを見つけるという一つの目的(実際には根底でそれぞれの思惑が違っているのであるが…)のもとで繰り広げる物語は常に一寸先は闇状態なのであり、約1か月間の怪獣調査行は毎日がドラマティックに高野さんを振り回すのであった。
個人的には「ゴリラ問題」がとても印象的である。ドクターはボア村の先住民にゴリラを食べるのは人道的(近代的)によろしくないと説く。が、ボア村の先住民は先祖代々ゴリラを捕まえて食べてきた。勿論生きるためである。人間社会のルールで生きるものと、地球上の生物のルールで生きるものとの考え方の違いであるわけだが、結局のところドクターもゴリラを撃ち、何だかんだと能書きを垂れて食べてしまうのである。
なんと人間の世界というものは勝手なものであろうか。どこの土地の先住民も皆、その地に生きる生き物の命を頂き、その命を繋げて来たのである。そこには人間だけが守られているという環境は存在しない。命を奪う(頂く)か、奪われるか、自分たちが生き残り、子孫を残していくために死と隣り合わせの戦いが厳粛に続いてきたのである。
ドクターが撃ったゴリラがボートの上に横たわる姿の描写に、何か後ろめたさの様な感覚を抱いた私も、ただ端から傍観しているだけの人間社会に守られた生き物なのであると強く感じた。
アフリカという(もっと言えば日本という島国を離れた時点で?)国土も大きければ、文化も人種も違う、全く未知で勝手な世界を手探りで切り拓き、突き進んで行くその感覚とは、起きる事態全てを俯瞰して捉え、抗うのではなく受け入れる寛容な精神が必要なのだろうと感じる。これは正に言うは易く行うは難しである。現代の汲々な暮らしをしている私はその心得を見習おうにも、その素質が無いのではないだろうかと思ってしまう。
高野さんは(今回のC.D.P.のメンバー皆は)最後までその巻き起こる事態に驚愕しながらも苦悩し、熟考し、そして楽しみ、更なる深みを求めているのであった。
「もっともっと想像のつかない世界に入っていきたい。そして願わくば、劇的な-今の自分の世界感を変えるようなー体験をしてみたい」(P302)とかたるその言葉は、やはり今の高野さんの活動に連綿と繋がっているのだと思う。
高野さんの書籍は沢山あって先立つものに不安を感じるが、私のフェイバリットである服部文祥先生、角幡雄介先生に並ぶ、高野秀行先生となったのは間違いなく、今後も引き続き高野ワールドを楽しんでいこうと思った。

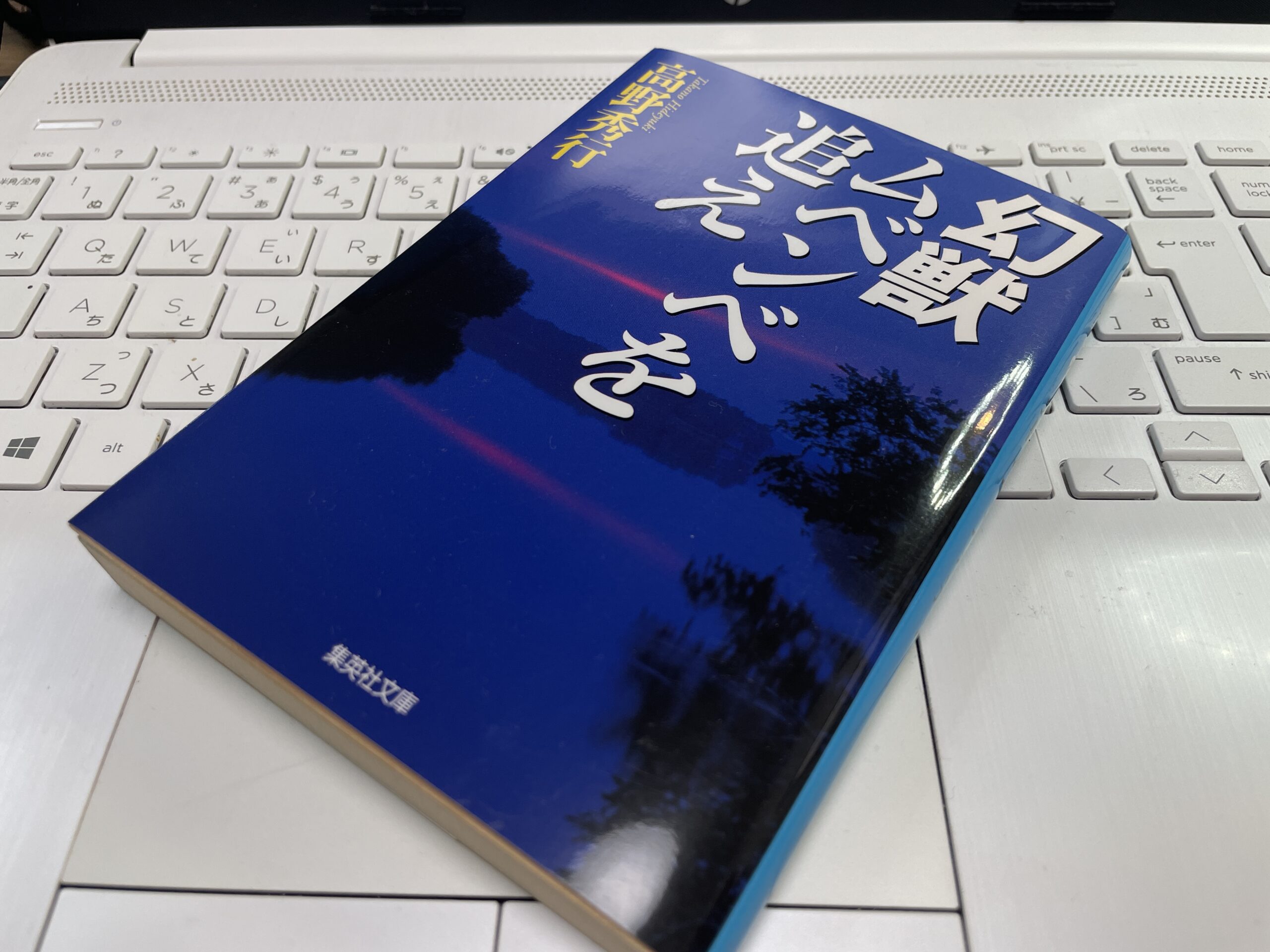



コメント