【タイトル】アムンセンとスコット
【著者】本多勝一
【出版社】 朝日新聞出版 (2021.12.30.発売)
完全に極地探検(紀行)物に傾倒しているなかで、本多勝一さんの本書に出会った。極地探検に人生を捧げたアムンセン。そして同時期に南極点初到達を目指すもアムンセンとの競争に敗れ、また悲運の遭難死を遂げたスコット。二人が、それぞれの隊を引率し挑戦した南極点争奪行進を、帰還したアムンセンや別隊員の日記、証言などをもとに本田勝一さんが時系列に沿い、同時進行する形で当時の状況を分析し検証する。
南極点初到達を果たしたのはノルウェーのアムンセン隊であるのは既知の事実であるが、その競争の勝敗を分けた要因とは何だったのか、二人の取り組んだ極地探検を深い洞察力で考察する。テンポよく展開する(切り取られた)両隊の極地行進を判り易い文章と、ふんだんに盛り込まれた南極大陸の状景や当時の極地生活の様子、そして隊員たちの写真で、読み手は道中の苦楽を追体験することになるだろう。
本書では、人類はなぜ極地を目指すのか、そしてその探検史に始まり、二人の出自や母国の地理的背景、国家戦略などから、それぞれがどのような影響を受け極地探検へ突き進んだかを考察する。
【極限(極地)での実力の差とは…】
南極点へ向けた行進の両隊による熾烈な争い(実際は両隊が戦うわけではなく、極点という過酷な環境、自然との対峙を指す)や、その前年のデポ作戦などにおいて、結果を述べるとアムンセン隊の圧倒的な勝利であった。
アムンセン隊は全体の行動を犬橇で行う事、またその機動力に長けた犬でさえ、最後は隊員が生きながらえるための計画的な食料と考えていた。またアムンセンは従える隊員たちの意見も尊重し、物理的な精神的安定(デポを見失わない工夫やテント内では個人的余裕=スペースを確保、無理な行進は望まず、行動能力も計画的配分に気を遣うなど)を保ち、柔軟にチームを引っ張り、極点からの帰路では食料デポも順調に回収、余りある食料を得ながら遂にはフラムハイツに帰還するのであった。決して天候に恵まれたなどという運が良かっただけの話ではなく、アムンセンの極地探検に対する心構えや準備、時には厳しい計画など、すべてが機能した結果だったのだろうと思う。
極点初到達を遂げた彼らの凱旋行進は、さぞや晴々とした素晴らしい旅であったのだろう。
かたやスコット隊はというと、前年に行った食料デポ作戦(目標の到達点まで届かず)での失敗を挽回する事が出来ず、終始苦難の連続を強いられることとなった。こちらも不運としかいいようがないのかもしれないが、やはりアムンセン隊と比較してしまうと、極地に対する考え方が何事に対しても不足していた様に思われる。
つまり、各隊のリーダーであるアムンセンとスコットの極地に対するそれまでの知識、備え、経験や実績など多々要因もあるが、その結果(実力)の差とは、そもそもの極地に対する情熱や憧れの大きさに帰結したのではと私は感じた。
【総括】
「史上最大の冒険レース」を迫真の展開で書かれた本書は、結果、私にとって極点を勉強するうえで非常に学びの多い「極点参考書」になった言っても過言ではない。本書を読む限りではスコット隊の余りにも不用意な、そして不運な場面が多々見受けられるように感じるが、スコット自身も初めての極点探検ではなく、シャックルトンと地球最南地点を旅した経験など、イギリス国きっての有力探検家であったはずである。
現在、イギリス隊側からの極点行進の記録も知っておかないと不公平になるかもしれないという思いから、「世界最悪の旅」(チェリーがラード著)を読み進めているところであるが、私には少し読みつらい翻訳で、これがなかなか捗らない。こちらの話もいずれまた感想を書きたいと思う。
なお、本書巻末の山口周さんによる解説が非常に鋭い視点でこの極点レースを分析されており、「組織とリーダーシップ」という問題を考える格好のケーススタディであると結ぶ。たしかに現代に生きる勤め人の我々にもお勧め?の一冊だろう。是非ご一読頂きたい。

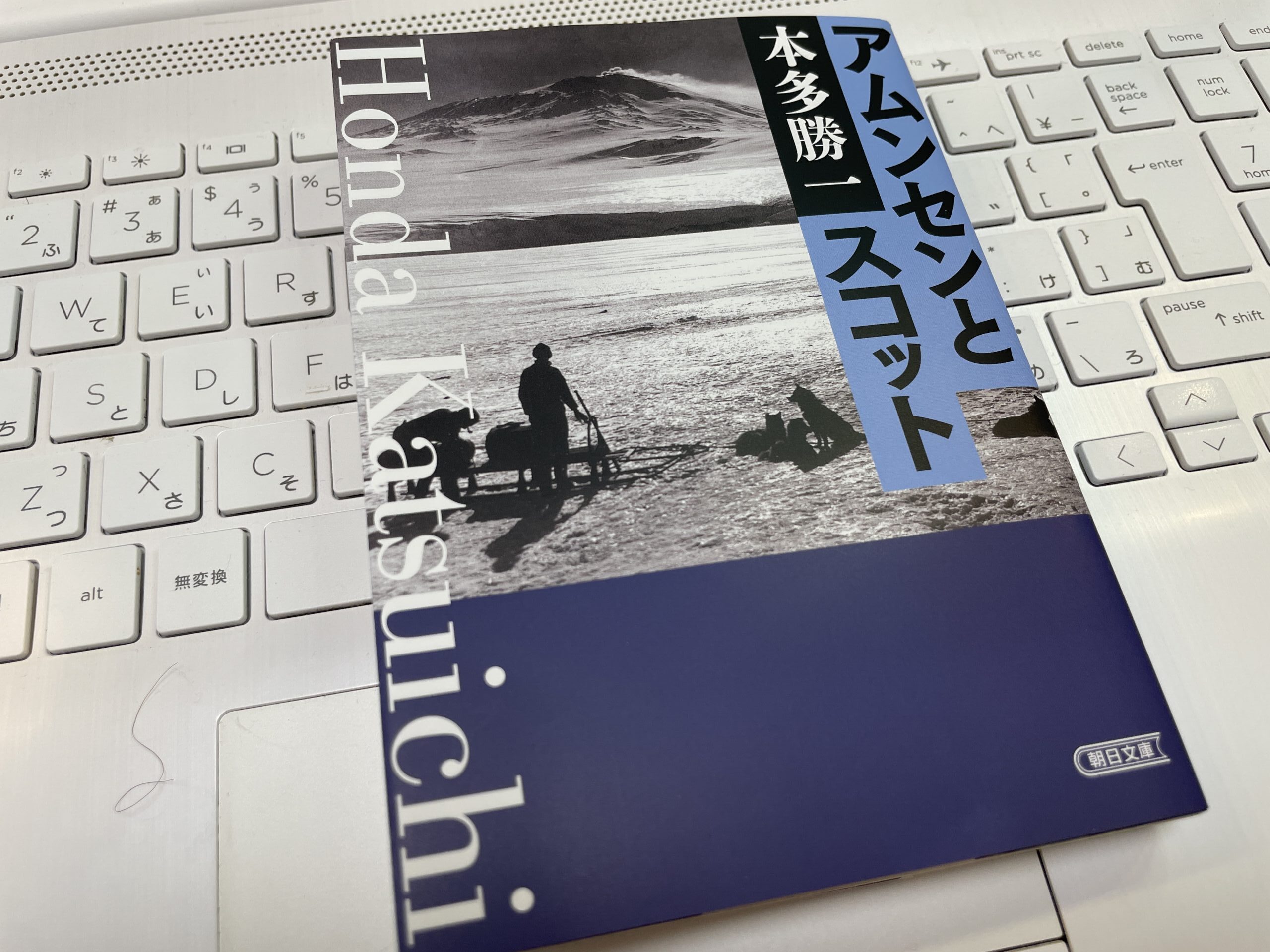


コメント